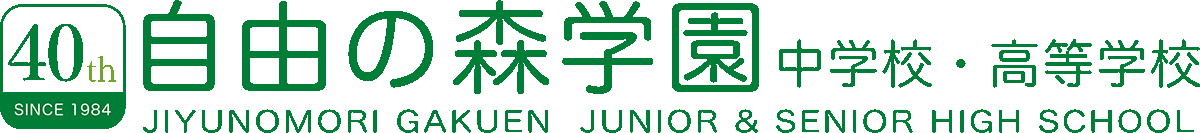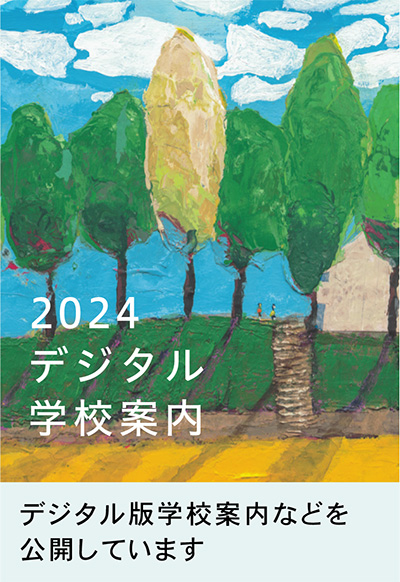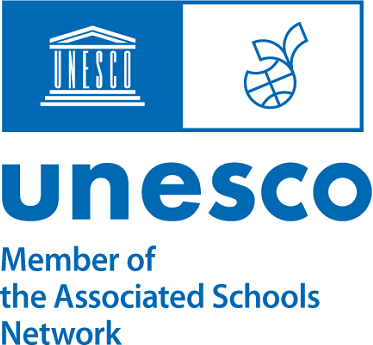開校。アンチテーゼから内実の在り方へ
「自由」という言葉の二面性
ただ、この時の決定について、私はいまだにそれでよかったのかと思うことがあります。「自由」という言葉のイメージが人々に誤解を与えてしまう部分もあって、本当は「ものをじっくり考えたり創り出したり、授業で話し合いながら学ぶ内容を深めて生きる力を育てる」とか、そういうことが主題だったはずなのに、どうも「自由」という名前ばかりが突っ走ってしまったところがあったなと。
それでも、やはりその名前のインパクトの強さによって、人がどっと集まってきたところもあったでしょう。当時、学校に集まってきた多くの人々の思いを「自由の森」という名前が吸収していたことは間違いありません。

黎明期の気づきと苦悩
1985年の開校が決まると、その前年から急ピッチで工事が進み、教員採用の準備も始まりました。公募したところ400通以上の応募があって、その中から50人くらいの方を選んで面接させていただいて、さらに半分の方に模擬授業をお願いして選考しました。
創立当時の学園の雰囲気は、何よりも「授業の面白さ」を評価されて採用された当時の教員たちと、初めての入試によって集められた1期生たちの個性によってつくり上げられたところが大きかったと思います。
当時はとくに、それまでの管理教育や詰め込み教育に対する問題意識が出てきた頃でした。子どもたちの間では元気な反発心も生まれて、尾崎豊の「夜の校舎、窓ガラス壊してまわった」なんて歌詞に象徴される時代でしたよね。
登校拒否(今でいうところの不登校)という言葉も社会問題として浮かび上がってきていた。そういう中で、教育について深く考えている人たちは、従来の教育に対する疑問を持っていて、そういう層の人たちが求めているものの中に学園はあったのだと思います。極端に言えば、自由の森学園は、あの時代でなければ生まれなかった学校だったのかもしれません。
そして、学校ができるまでは「校則がない」「序列がない」という一般教育へのアンチテーゼを前面に押し出していたら良かったわけですが、いざ学校が始まると、「じゃあいったい何があるの?」ということが問われ始めました。教育の質というか、内実の問題です。創立当初は、とくにそれをつくり出す大変な作業を始めた頃だったのだなと、今振り返って思い出されます。